不安てあって当たり前なんだそうですよ!
今週、レッスンの前に生徒さんにお話しさせていただいた話を、ぜひ皆さんともシェアしたいなと思ってコラムに書こうと思います。
それは「不安」というものについてです。
これを読んでいるあなたは、今感じている不安てどんなことですか?
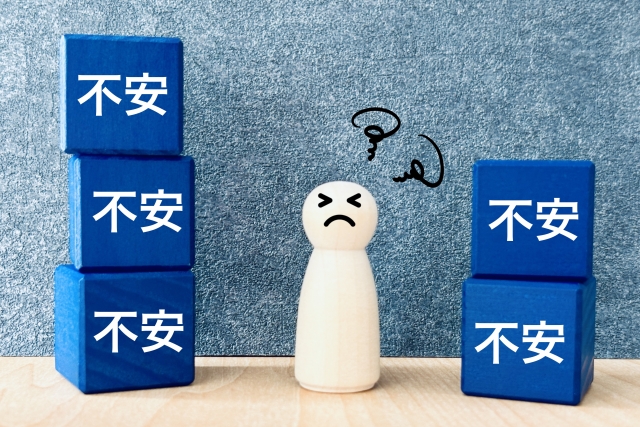
東北大学の先生で、河田雅圭先生がお話しされていたんですが、そもそも前提として、私たち人間は不安がなければ死んでしまう、と。
だから、不安があるということは、生命を維持する上でとても大切だということなんです。
その先生のお話で特に興味深いなと思ったのが、まず、私たちは元々私たちは猿だったわけですが、その進化の過程で、猿と人とでは「不安」を規定したり、それを表したりする遺伝子、アミノ酸の配列が違うそうなんです。
具体的にどうやって研究されたのかは私も詳しくは分からないんですが、その研究によると、猿の方が人間よりも不安を感じにくい、と。つまり、人間の方が不安を感じやすいために、その不安を解消しようと進化を遂げてきた、というわけですね。
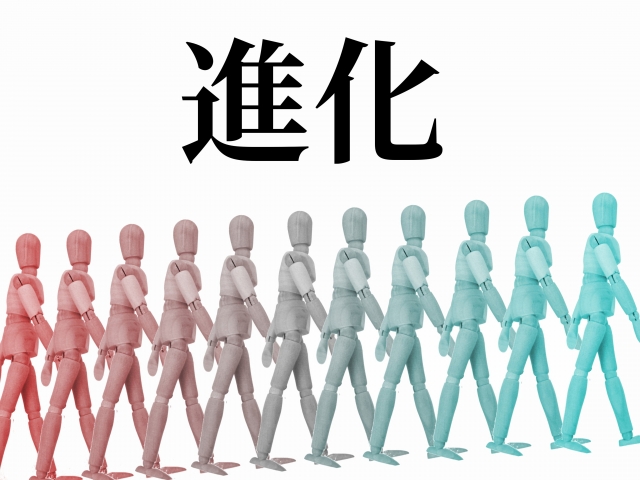
さらに面白いのが、人間の進化の過程で遺伝子の突然変異が起こったそうなんです。それによって、ベースとして猿と比較して不安を感じやすいタイプの人間と、さらにそれよりも不安を感じにくいタイプの人間、この2種類の遺伝子配列を持つ人々が生まれた、と。
今、この地球上には、その2種類の遺伝子を持つ人間がいるそうなんですが、いわゆるグレートジャーニー、人がアフリカ大陸から世界中に広がっていった過程を考えると、不安を感じにくい遺伝子を持つ人々、つまり後から突然変異で生まれたタイプの人々は、どんどんとアメリカ大陸の方へ進んでいったそうなんです。
ね、これ面白くないですか?
では、日本人はどうなのかと言うと、どちらかというと不安を感じやすい方の遺伝子を持つ人の割合が高いそうなんですね。ここで大きく関わってくるのが、狩猟民族だったか、農耕民族だったか、ということです。
私たち日本人は元々、農耕民族として生活してきました。農耕というのは、作物を育てるわけですから、天候に左右されたりして、常に不安定さが伴いますよね。「今年はちゃんと収穫できるだろうか」「雨が降らなかったらどうしよう」といった不安が常につきまとう。一方で、狩猟民族というのは、ある意味ギャンブル的で、獲物が獲れる時はたくさん獲れるけれど、獲れない時は獲れない。不安を感じにくいからこそ、そういった生活様式が成り立っていたのかもしれません。
このように、不安という一つの要素をとっても、生活の営みには大きな違いが生まれてくる、というお話だったんですね。
この話を聞いて、私が思ったのは、ヨガ講師という立場から見ると、東洋思想と西洋思想の違いにも通じるものがあるな、ということです。
西洋思想は、どちらかというと外側に豊かさを求めて発展してきました。
だから、日本も含め東洋に比べて早い段階で車や電話といった便利なものが普及し、文明が開花しましたよね。
一方、東洋思想ではというと、外側に物の豊かさを求めても、そこに本当の幸せはないと考えます。
真理や道理といったものは、自分の内側にあると捉えるので、内面を探求することに時間を使ってきたわけです。自然と共に生き、自然を崇拝する中で思想が育まれてきました。
なので、この不安遺伝子の違いが、西洋の人々が外へ外へと何かを求めていった原動力なのか、それとも内側の豊かさを求める東洋的な生き方が、農耕民族という選択につながったのか…そのあたり、遺伝子がどこまで関係しているのか、とても気になるところだなと思いました。
来週もまた、レッスン前にこの「不安」についてさらに深掘りしたお話をしたいと思います!!